当ブログ記事では技術士倫理綱領について「丸暗記ではなく3義務2責務と関連させて “理解する” と効果的ですよ」と提案しています。
(2023年3月の改定に伴い再編集しています)
技術士倫理綱領について
技術士倫理綱領は日本技術士会WebサイトにアップされておりPDFでもダウンロードが可能ですが、こちらに挙げておきます。
【前文】に綱領についての概要説明があり、【基本綱領】に具体的な内容が記載されています。
技術士倫理綱領【前文】
技術士は、科学技術の利用が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に認識し、業務の履行を通して安全で持続可能な社会の実現など、公益の確保に貢献する。
日本技術士会Webサイトより引用
技術士は、広く信頼を得てその使命を全うするため、本倫理綱領を遵守し、品位の向上と技術の研鑚に努め、多角的・国際的な視点に立ちつつ、公正・誠実を旨として自律的に行動する。
技術士倫理綱領【基本綱領】
安全・健康・福利の優先
1.技術士は、公衆の安全、健康及び福利を最優先する。
(1)技術士は、業務において、公衆の安全、健康及び福利を守ることを最優先に対処する。
(2)技術士は、業務の履行が公衆の安全、健康や福利を損なう可能性がある場合には、適切にリスクを評価し、履行の妥当性を客観的に検証する。
(3)技術士は、業務の履行により公衆の安全、健康や福利が損なわれると判断した場合には、関係者に代替案を提案し、適切な解決を図る。持続可能な社会の実現
2.技術士は、地球環境の保全等、将来世代にわたって持続可能な社会の実現に貢献する。
(1)技術士は、持続可能な社会の実現に向けて解決すべき環境・経済・社会の諸課題に積極的に取り組む。
(2)技術士は、業務の履行が環境・経済・社会に与える負の影響を可能な限り低減する。信用の保持
3.技術士は、品位の向上、信用の保持に努め、専門職にふさわしく行動する。
(1)技術士は、技術士全体の信用や名誉を傷つけることのないよう、自覚して行動する。
(2)技術士は、業務において、欺瞞的、恣意的な行為をしない。
(3)技術士は、利害関係者との間で契約に基づく報酬以外の利益を授受しない。有能性の重視
4.技術士は、自分や協業者の力量が及ぶ範囲で確信の持てる業務に携わる。
(1)技術士は、その名称を表示するときは、登録を受けた技術部門を明示する。
(2)技術士は、いかなる業務でも、事前に必要な調査、学習、研究を行う。
(3)技術士は、業務の履行に必要な場合、適切な力量を有する他の技術士や専門家の助力・協業を求める。真実性の確保
5.技術士は、報告、説明又は発表を、客観的で事実に基づいた情報を用いて行う。
(1)技術士は、雇用者又は依頼者に対して、業務の実施内容・結果を的確に説明する。
(2)技術士は、論文、報告書、発表等で成果を報告する際に、捏造・改ざん・盗用や誇張した表現等をしない。
(3)技術士は、技術的な問題の議論に際し、専門的な見識の範囲で適切に意見を表明する。公正かつ誠実な履行
6.技術士は、公正な分析と判断に基づき、託された業務を誠実に履行する。
(1)技術士は、履行している業務の目的、実施計画、進捗、想定される結果等について、適宜説明するとともに応分の責任をもつ。
(2)技術士は、業務の履行に当たり、法令はもとより、契約事項、組織内規則を遵守する。
(3)技術士は、業務の履行において予想される利益相反の事態については、回避に努めるとともに、関係者にその情報を開示、説明する。秘密情報の保護
7.技術士は、業務上知り得た秘密情報を適切に管理し、定められた範囲でのみ使用する。
(1)技術士は、業務上知り得た秘密情報を、漏洩や改ざん等が生じないよう、適切に管理する。
(2)技術士は、これらの秘密情報を法令及び契約に定められた範囲でのみ使用し、正当な理由なく開示又は転用しない。法令等の遵守
8.技術士は、業務に関わる国・地域の法令等を遵守し、文化を尊重する。
(1)技術士は、業務に関わる国・地域の法令や各種基準・規格、及び国際条約や議定書、国際規格等を遵守する。
(2)技術士は、業務に関わる国・地域の社会慣行、生活様式、宗教等の文化を尊重する。相互の尊重
9.技術士は、業務上の関係者と相互に信頼し、相手の立場を尊重して協力する。
(1)技術士は、共に働く者の安全、健康及び人権を守り、多様性を尊重する。
(2)技術士は、公正かつ自由な競争の維持に努める。
(3)技術士は、他の技術士又は技術者の名誉を傷つけ、業務上の権利を侵害したり、業務を妨げたりしない。継続研鑽と人材育成
日本技術士会Webサイトより引用
10.技術士は、専門分野の力量及び技術と社会が接する領域の知識を常に高めるとともに、人材育成に努める。
(1)技術士は、常に新しい情報に接し、専門分野に係る知識、及び資質能力を向上させる。
(2)技術士は、専門分野以外の領域に対する理解を深め、専門分野の拡張、視野の拡大を図る。
(3)技術士は、社会に貢献する技術者の育成に努める。
読み方は最初におさえておこう
倫理綱領の漢字の読み方は「りんりこうりょう」です。念のため。
口頭試験で読み方を間違えていると恥ずかしい(& 回答の説得力ダウン)ので最初におさえておきましょう。
技術士倫理に関するブログ記事を下記リンク先にまとめてみました。
倫理に関する対策学習はこちらのページをブックマークしておけば時短できます。
→ 技術士倫理の総まとめ【一次・二次・口頭試験の重要ポイントも】
技術士倫理綱領は3義務2責務と一緒に関連させて理解しよう
3義務2責務については、技術士を目指す上で最初に学習すべきものです。
詳しくはこちらのブログ記事で説明しています。
→ 技術士 3義務2責務について【覚え方のコツ】
今回のブログ記事では技術士倫理綱領との関係について説明します。
技術士倫理綱領は具体的な行動指針に落とし込んだもの
3義務2責務は文字通り3つの義務と2つの責務について述べています。
一方で技術士倫理綱領は10項目があり、前文の最後に「~行動する」と書いてあります。
倫理綱領の各内容を読んでみると、それぞれが3義務2責務のどれかに包含されていることがわかります。
よって倫理綱領はさらに具体的な行動指針に落とし込んだものと考えてよいです。
対応する技術士倫理綱領の分類
3義務2責務それぞれについて、技術士倫理綱領がどのように対応しているか分類してみました。
| 3義務2責務 | 対応する倫理綱領 |
|---|---|
| 信用失墜行為の禁止 | 真実性の確保 |
| 公正かつ誠実な履行 | |
| 信用の保持 | |
| 法令等の遵守 | |
| 秘密保持義務 | 秘密情報の保護 |
| 名称表示の場合の義務 | 有能性の重視 |
| 相互の尊重 | |
| 公益確保の責務 | 安全・健康・福利の優先 |
| 持続可能な社会の実現 | |
| 資質向上の責務 | 継続研鑽と人材育成 |
倫理綱領の10項目がどれに対応するか見ておきましょう。
技術者倫理に関する質問を受けた際に、質問に答えてさらに「技術士倫理綱領にも○○として定められています」といった感じで補足できれば説得力が増します。
技術士倫理綱領の覚え方【暗記するより理解して考える】
技術士倫理綱領は10項目もあるので個々について文言を丸暗記する必要は無いでしょう。
ただしその存在や目的については説明できる様にしておくべきです。
口頭試験において「倫理綱領とはどのようなものか知っていますか」と問われたら、
「3義務2責務は技術士が果たすべき3つの義務と2つの責務です。倫理綱領はその内容について、さらに具体的な行動指針として10項目が挙げられています」
といったレベルの説明ができるようにしておきましょう。
暗記しても意味がない【理解して自分のものにしよう】
文章を「丸暗記」しても意味がありません。
3義務2責務も技術士倫理綱領も「技術士として理解すべきこと」です。
重要なのは「意味を理解しているかどうか、自分の考えとしているかどうか」です。
口頭試験では「技術士の持つべき倫理感について理解しているか、考えているか」を確認する質問を受けるハズです。
意味を自分のモノにできておらず、ただ丸暗記しても「読み上げてください」という質問にしか答えられないです。
3義務2責務と倫理綱領の実際の事例を語れるようにしておこう
こちらの3義務2責務に関するブログ記事の後半”口頭試験で押さえておくべき大事なこと” においても述べていますが、“あなたがどう思うか” について聞かれた時の想定をしておきましょう。
具体的な事例について聞かれた場合に、核心部分を一通り説明したあとで、
「これは技術士が果たすべき3義務2責務の○○の義務(責務)にも該当し、また具体的な行動指針として技術士倫理綱領にも△△として挙げられています」
とスムーズな流れで補足説明できれば理解のアピールに繋がります。
技術者の倫理に関する想定問答集を作るときは想定の回答に、
「3義務2責務のどれに該当するか」
「倫理綱領のどれに該当するか」
について関連させて答えられるようにしておきましょう。
技術士倫理に関するブログ記事を下記リンク先にまとめてみました。
倫理に関する対策学習はこちらのページをブックマークしておけば時短できます。
→ 技術士倫理の総まとめ【一次・二次・口頭試験の重要ポイントも】
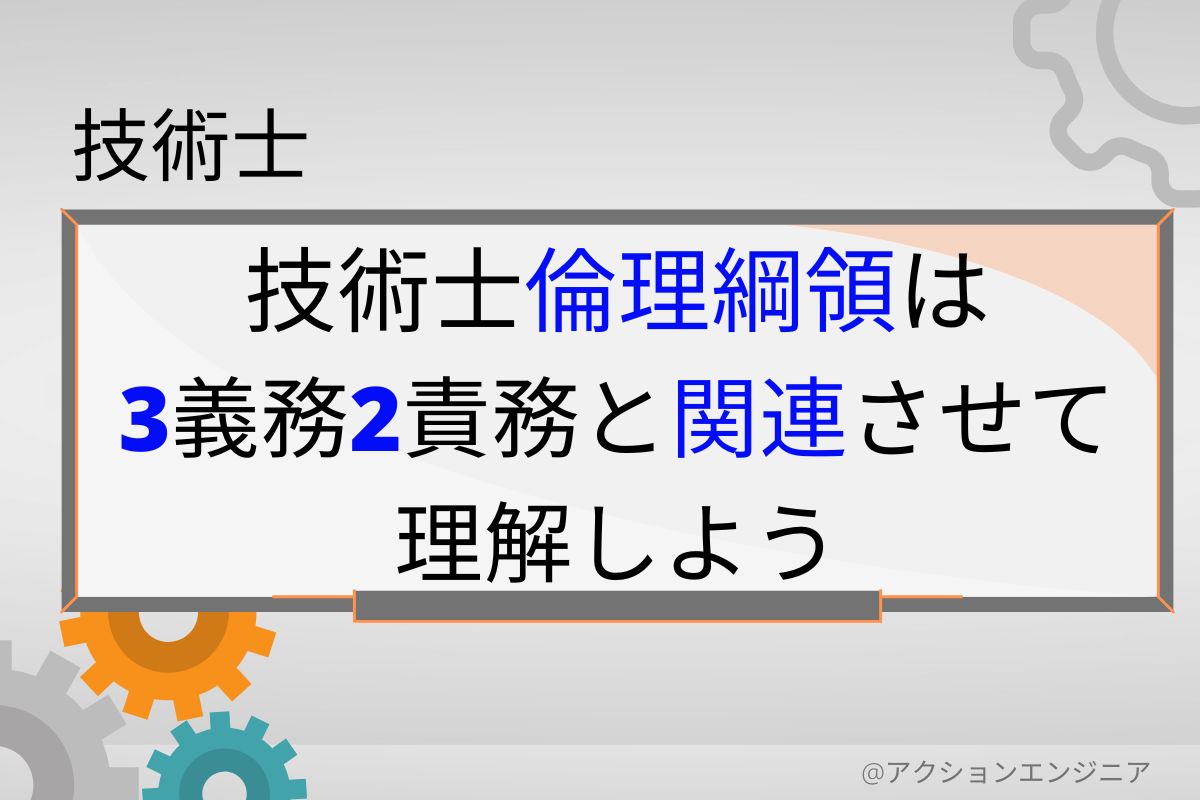
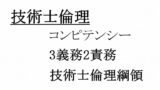
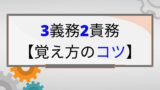
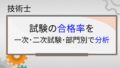

コメント