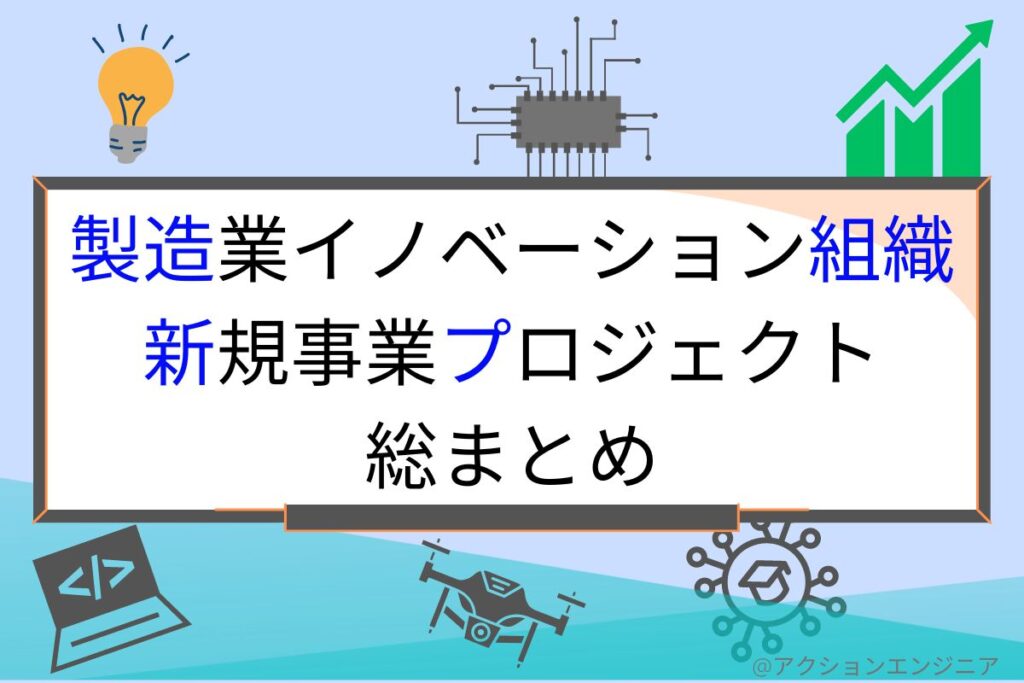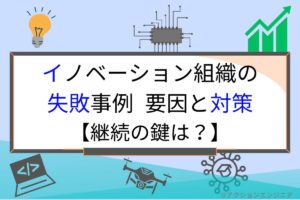イノベーション関連おすすめ本の紹介【組織論や開発・新規事業プロジェクトの進め方を学ぶ】
イノベーションや開発組織、新規事業プロジェクトの創出活動に関するおすすめ本を紹介しています。
製造業に20年間在籍し、専門職大学院にて開発設計や体系について学んだ経験をもとに、開発活動やフレームワーク、運営組織について考える事前知識としておすすめの本を紹介します。
Contents【クリックできる目次】
イノベーションのジレンマ【クレイトン・クリステンセン】
イノベーションについて書かれた書籍の中で最も有名といってもいいのがこの本「イノベーションのジレンマ」ではないでしょうか。
なので、時間がない人はとりあえずこの本だけでも読みましょう笑。
著者のクレイトン・クリステンセンはイノベーション関連で非常に有名な経営学者で多くの書籍を執筆していますが、この本が最も有名です。
企業におけるイノベーション創発の難しさ、開発活動のジレンマについて、その理由を掘り下げて実感できます。
イノベーションのジレンマ 増補改訂版 Harvard business school press
製造業にて開発と現場に向き合っていた私にとって、以下はとても納得感がある内容でした。
イノベーションのジレンマが発生する理由
- 企業は短期的利益を重視する株主や収益確保に重要な既存顧客を優先する
- イノベーション初期は市場規模が小さいため、大企業は参入価値を見出しにくい
- 市場が存在しない、小さい場合、そこに参入するための分析が難しい(説明根拠が作れない)
- 企業は既存事業の能力を高めているため、異なる事業の推進が難しい
- 技術力を高めることと、そこに需要があることはイコールではない
イノベーションのジレンマより 抜粋して要約
まずはこの書籍を読んで、企業における開発組織や体制について考えるのがおすすめです。
恐れのない組織 「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす
この本「恐れのない組織」の著者のエイミー・C・エドモンドソンは心理的安全性を提唱したことで有名です。
心理的安全性が確保されていない状況を簡単に言うと
「チャレンジに失敗したら責任を取らされるかも」
「こんなこと言ったら怒られるのではないか、バカにされるかも」
といった感覚です。
書籍の副題にあるように、組織におけるイノベーション創出や学習・成長において、重要視されています。
お互いに信頼関係や心理的安全性が確保されていない場合、自発的な発言や行動が控えられたり、反対意見が言えなくなったりして、多様性が確保されなくなってしまう傾向にあります。
開発・企画のチームリーダーや課長クラスの人などチーム員の雰囲気を作る必要のある人におすすめの書籍です。
恐れのない組織――「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす
両利きの経営
チャールズ・A・オライリーが書いた「両利きの経営」日本語訳 です。
両利きの経営とは「既存事業の深堀」と「新規事業の探索」を両立させる経営理論の事です。
企業にとって現状の経営を維持・伸展するために利益を確実に確保・最大化するための既存事業は最も重要です。
一方で数年先、数十年先、それ以上に企業が永続していくためには既存事業の深堀だけでは不十分です。
時代のニーズや社会の変化に合わせて新規事業を探索し、その探索した新規事業を利益に変える、継続的な事業に結び付けていく必要があります。
この書籍「両利きの経営」では、「既存事業の深堀」と「新規事業の探索」という異なる面を持った企業活動をどのように両立させて、どちらも成功させるにはどうしたらよいか、に関する手法や経営論を学ぶことができます。
両利きの経営(増補改訂版)―「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く
両利きの組織をつくる
こちらの「両利きの組織をつくる」という本は上述の「両利きの経営」に関して「日本企業における両利きの経営をどのようにすればいいのか」という視点で書かれています。
前述の「両利きの経営」がちょっと分厚い本なので、時間のない人はこちらの書籍で「両利き経営」について理解するのもいいですね。
日本人の著者なので感覚的にも納得できる部分が多く、エンジニアであり大学院で組織論・経営論の初学者であった私にとってもわかり易く学ぶことができました。
ステージゲート法 製造業のためのイノベーションマネジメント
こちらの書籍「ステージゲート法」は「製造業のための~」と副題がありますが、プロジェクトマネジメントの流れを学ぶにも非常におすすめです。
プロジェクトや開発テーマを進捗によってステージ(フェーズとも呼ばれる)を設定し、そのステージを進むためにゲートを設置し、ゲートのタイミングで評価を行います。
このゲートにおける評価の視点、度合い、評価者について、ステージを進むごとに変えて(難易度を上げて)いきます。
多くの企業のプロジェクトマネジメントにおいて導入されている開発手法のフレームであり、製造業だけでなく会社員であれば心当たりのある人が多いと思います。
どのようになレベルの概念でステージを分けるのか、ゲートにおける評価視点など、一般的な話や他企業の実例もあるので、自社のプロジェクトマネジメントと比較してみると参考になります。
2040年の未来予測
こちらの書籍「2040年の未来予測」は題名の通り予測本です。
読んでいると様々な視点からの予測について触れる重要性に気付かされます。
そんな視点、考えに触れて「自分で予測する力、考える力」を養うのにとてもおすすめな本です。
(この本でなくても、未来予測本は著者によって視点が異なるので複数読んでみると面白いです)
個々のイノベーションを考える、開発テーマを選定する時にやはり未来を見据えることは重要です。
iPhoneが発売されてからまだ14年しか経っていないんですね。
あらためて振り返るとすごいスピードで世の中が進歩していることがわかります。
使用者の視点だけでなく、関連産業や関連技術(半導体、カメラ、電池、画面etc)についても非常に大きなインパクトを与えています。
「未来を予測する」ということについて、ただ単に知識や情報を集めることももちろん大事なのですが、現在の状況や実現可能な技術を客観的に見て「将来の方向性を予測する」ことが重要なのだという感想を持ちました。
以上、、イノベーション組織や活動に関係する上で勉強になる&おすすめしたい書籍を紹介しました。
参考にしていただけたら幸いです。